「痛み」は脳が生み出すアウトプット
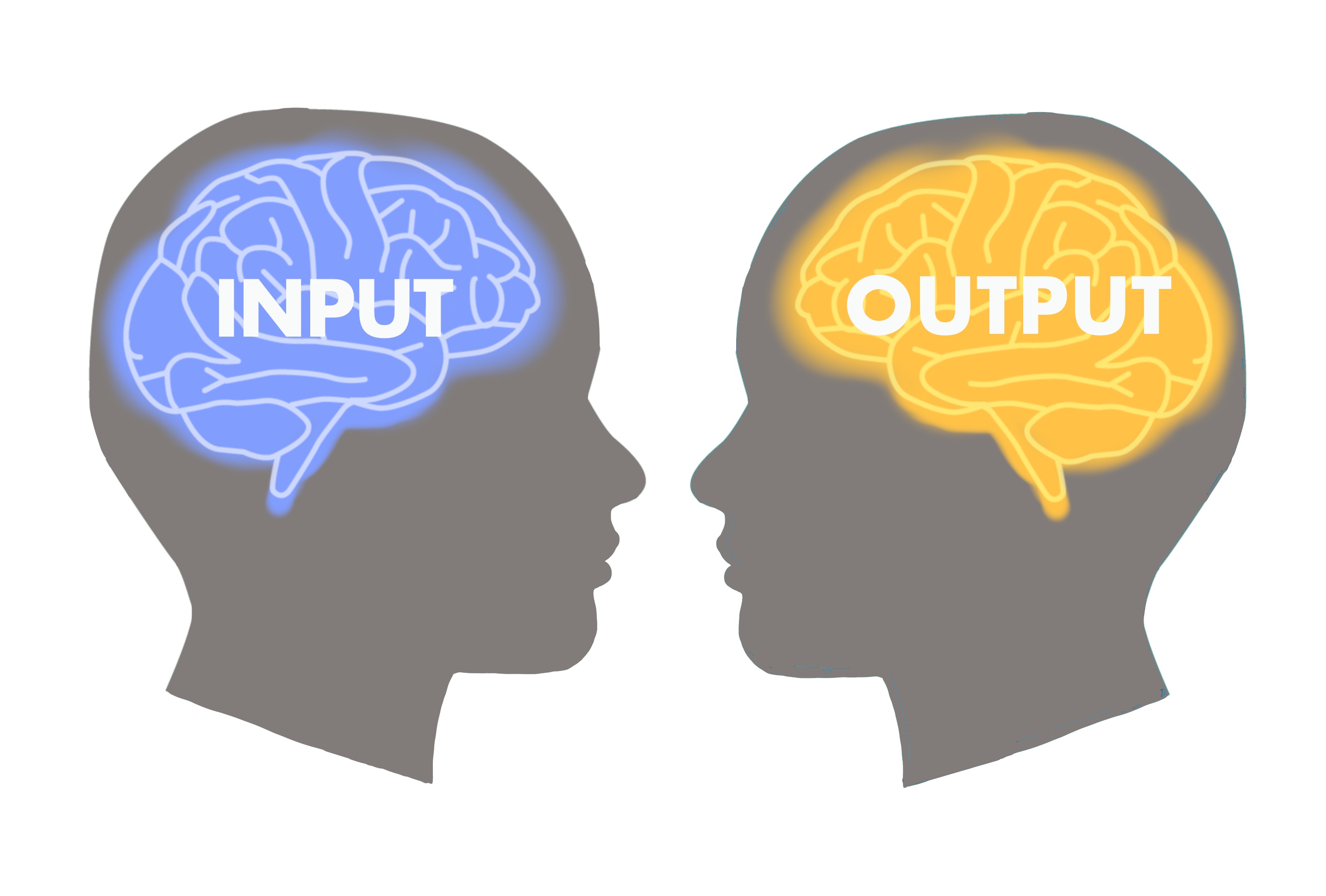
「痛み」は、単に体の組織が傷ついた結果ではなく、脳が処理した情報のアウトプットとして生じます。つまり、同じ刺激を受けても「痛い」と感じるかどうかは、脳の状態によって変わるのです。
例えば、スポーツ中にケガをしても気づかないことがある一方で、何も触れていないのに痛みを強く感じることもあります。
これは、痛みが単なる入力(刺激)ではなく、脳が作り出しているからです。
痛みの仕組みを詳しく見ていきましょう。
1.痛みの入力 〜体のセンサーがキャッチ〜
皮膚・筋肉・関節などにある侵害受容器(センサー)が、痛みのもととなる刺激をキャッチします。
- ケガや圧迫による機械的刺激(転倒・打撲・切り傷など)
- 熱さや冷たさによる温度刺激(火傷・凍傷など)
- 炎症や疲労物質による化学的刺激(腫れ・乳酸の蓄積など)
- 血流不足による虚血性の痛み(筋肉のこわばり・しびれなど)
痛みを感じるかどうかは、脳の判断に委ねられているためこの刺激が必ずしも「痛み」になるとは限りません。
2.痛みの伝達と調整 〜脳が痛みを決める〜
痛みの信号は、神経を通じて脊髄に送られ、最終的に脳で処理されます。
特に、以下の脳の部位が「痛みの認識」に関わります。
| 脳の部位 | 役割 |
|---|---|
| 体性感覚野 | 痛みの位置・強さを判断 |
| 前帯状回(ACC) | 痛みの不快感・ストレスを生み出す |
| 島皮質 | 痛みと感情を結びつける |
| 扁桃体 | 過去の記憶と痛みを関連づける |
「痛み」は単なる刺激ではなく、脳が総合的に処理し、「痛い」と認識して初めて生じるものなのです。
3.脳の状態で痛みは変わる
脳の働きによって、まったく同じ刺激でも痛みを感じたり、感じなかったりすることがあります。
① スポーツ中に痛みを感じにくい(痛みの抑制)
スポーツや戦闘など集中が必要な状況では、脳はエンドルフィン(脳内麻薬)を分泌し、痛みを感じにくくします。
例えば…
- サッカー選手が試合中に足を捻挫しても気づかず、試合後に痛みを感じる。
- マラソン中は足が痛くないのに、ゴール後に痛みが一気に出てくる。
このように、脳が「今は痛みを感じている場合ではない」と判断すると、痛みの信号をブロックします。
② うつ症状やストレスで痛みが増す(痛みの増幅)
ストレスやうつ症状があると、痛みを強く感じやすくなります。
これは、セロトニンやノルアドレナリンなどの痛みを抑制する物質が不足するためです。
例えば…
- 慢性的なストレスが続くと、肩こりや腰痛がひどくなる。
- うつ症状があると、以前は気にならなかった小さな痛みが強く感じられる。
③ 過去の経験が痛みを左右する(記憶の影響)
過去に強い痛みを経験すると、その記憶が「痛みの回路」を強化し、同じ状況で痛みを感じやすくなることがあります。
例えば…
- 以前、ギックリ腰をした経験がある人は、少し腰に違和感があるだけで「また痛くなりそう」と感じ、痛みが強まる。
- 注射が苦手な人は、針が見えただけで痛みを感じる。
これは、脳が「この状況は危険」と判断して、痛みを強調するために起こります。
④ 痛そうな映像を見ると自分も痛くなる(共感と痛み)
脳には「ミラーニューロン」と呼ばれる、他人の行動を自分のことのように感じる神経細胞があります。これが、痛みの認識にも影響を与えます。
例えば…
- 映画やスポーツの映像で選手がケガをするシーンを見ると、自分の体にも違和感を覚える。
- 誰かが紙で指を切るのを見たとき、自分の指もゾワッとする。
これは、脳が「他人の痛み」をシミュレーションしてしまうために起こります。
4. 痛みをコントロールするためにできること
痛みは、単に「体の一部が傷ついている」だけでなく、脳の状態によって大きく変わることをお解りいただけたと思います。
痛みを和らげるには、以下のようなアプローチが有効です。
- 筋膜リリース・ストレッチで筋肉の過緊張を和らげる
- トリガーポイント療法(鍼・マッサージ)で痛みの信号を抑制する
- 運動や入浴で血流を改善し、痛みを誘発する物質を体外に排出するように促す
- リラックスする時間を作り、ストレスを軽減する
- 痛みへの意識を変え、「痛み=危険」ではないと脳に学習させる
- 正しい動きを獲得し、同じ動きを繰り返しても脳が反応しないようにする(動きの多様性を獲得する)
「痛み=脳のアウトプット」であることを理解し、上記のような適切なアプローチを行うことで、痛みのコントロールが可能になります。
- 痛みは、脳が生み出すアウトプットである
- スポーツ中の集中やエンドルフィン分泌で、痛みは感じにくくなる
- ストレスやうつ状態では、逆に痛みが増幅する
- 過去の経験や映像を見ることでも、痛みを感じることがある
- 適切なケアで、脳と体の痛みを整えることができる
※当院の院長の小井手智啓は鍼灸師として19年間第一線で活躍しており、日本で代替医療に分類されている国家資格を持っております。また、筋膜ストレッチ(朝日新聞 2016年出版)の監修を歴任するほど、肩こり、腰痛、頭痛をはじめ、多くの現代人が悩む痛みやコリの改善について、その経験と知識を高く評価されております。

